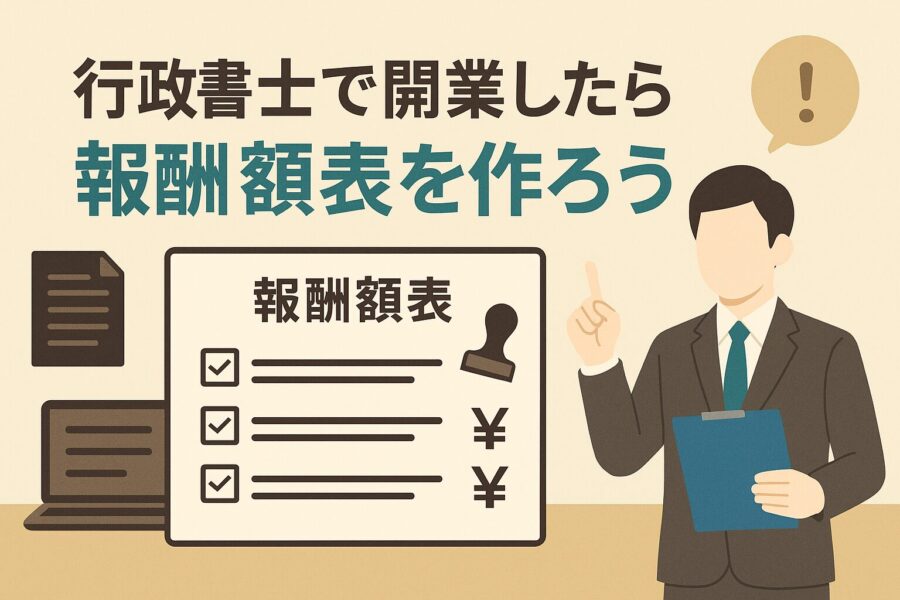
行政書士登録が完了し、いよいよ開業!期待に胸を膨らませる一方で、事務所運営には様々な準備が必要です。
その中でも、特に新人行政書士の方が頭を悩ませるのが「報酬額表」の作成ではないでしょうか。
法律で義務付けられているとはいえ、右も左も分からない状態で自分のサービスに値段をつけるのは至難の業です。
高すぎれば誰も依頼してくれませんし、安すぎれば経営が成り立ちません。
この記事では、これから開業する行政書士の皆様が、自信を持って報酬額表を作成し、適切な料金設定を行うための具体的な方法とヒントをご紹介します。
この記事を最後までお読みいただければ、報酬額表作成の全体像を把握し、開業後の料金設定に関する不安を解消できるはずです。
開業行政書士に「報酬額表」の掲示が義務付けられている理由
行政書士として開業し、事務所を構えるにあたり、必ず準備しなければならないものの一つに「報酬額表」があります。
これは単なる料金リストではなく、行政書士法によって事務所の見やすい場所に掲示することが義務付けられている重要な書類です。
行政書士法第10条の2
行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
なぜ、報酬額表の掲示が義務付けられているのでしょうか?
その最大の理由は、お客様への情報提供と透明性の確保にあります。
お客様が行政書士事務所に来所された際に、依頼を検討している業務について、どれくらいの報酬がかかるのかを事前に目で見て確認できるようにするためです。
これにより、お客様は安心して依頼を検討することができ、行政書士側も報酬に関するトラブルを防ぐことができます。
お客様との信頼関係を構築する上で、報酬額表の掲示は極めて重要な意味を持つのです。
新人行政書士が直面する報酬額設定の壁と乗り越え方
経験豊富な行政書士であれば、過去の実績や業務にかかる時間、難易度などを考慮して適切な報酬額を算出することができます。
しかし、開業したばかりの新人行政書士にとって、これは非常に高いハードルとなります。
やったことのない業務に対して、どれだけの工数がかかり、どれくらいの価値があるのかを見積もるのは容易ではありません。
ここで料金設定を誤ると、お客様からの依頼が得られないだけでなく、自身の事業継続が危うくなる可能性すらあります。
では、右も左も分からない新人行政書士は、どのように報酬額を決めれば良いのでしょうか。
主に参考となるのは以下の2つの方法です。
- 所属行政書士会が公表する統計データを参考にする
- 近隣の行政書士事務所のホームページ等で料金を参考にする
これらの情報を上手に活用することが、新人行政書士が報酬額設定の壁を乗り越えるための現実的な第一歩となります。
報酬設定の参考にすべきデータと地域性の重要性
行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の利便性向上や行政書士の業務の参考とするため、報酬額に関する統計を作成し、公表するよう努めています(行政書士法第10条の2第2項参照)。
この統計データは、特定の業務について全国平均の報酬額が示されており、多くの行政書士がこの平均額を基準に報酬額を決定していると考えられます。
全国的な相場を知る上で非常に有用であり、特に経験のない業務の価格設定において、最初に参照すべき情報の一つと言えるでしょう。
ただし、この統計データは行政書士登録を完了した会員しか閲覧できません。
行政書士法第10条の2 2項
行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
しかし、行政書士の業務には、地域ごとの条例や慣習によって手続きの難易度や求められる書類が異なるものが少なくありません。
例えば、特定の許認可申請において、自治体によって解釈や必要書類が異なる場合があります。
そのため、全国平均のデータだけではなく、ご自身の事務所がある地域の特性を考慮することが非常に重要です。
ここで有効なのが、近隣の行政書士事務所のホームページ等を参考にすることです。
地域の行政書士がどのような業務にいくらくらいの料金設定をしているかを確認することで、その地域の実情に合った適正な報酬額を見出す上での貴重な情報が得られます。
報酬額は個々の行政書士が自由に設定できるものですが、これらの情報を活用し、市場感や地域の慣習を理解した上で設定することが、お客様からの信頼を得るためにも、また自身の事業を継続するためにも不可欠と言えるでしょう。
全国平均と地域の実情のバランスを見極めることが、適切な料金設定のカギとなります。
報酬額表の具体的な作成手順と作成後の注意点
報酬額の目安が定まったら、いよいよ報酬額表を作成します。
義務付けられている「掲示」という目的を果たすためには、お客様に見やすい形式で作成する必要があります。
実際に報酬額表を作成する手順は、行政書士会が提供しているひな形(テンプレート)を利用するのが最も効率的で確実です。
行政書士会では、会員向けに報酬額表のテンプレートをホームページで公開しています。
一般的な作成手順は以下の通りです。
- 所属行政書士会のホームページ等から報酬額表のひな形(テンプレート)をダウンロードする。
- ご自身が提供したい(または提供する可能性のある)業務名と、それぞれに設定した報酬額をひな形に入力する。 業務名は、お客様に分かりやすいように具体的に記載しましょう。報酬額は、これまでの検討結果(統計データ、近隣相場、地域性など)を反映させます。
- 作成した表を印刷する。
- 印刷した報酬額表の定められた場所に職印を押印する。 職印の押印は、その報酬額表が事務所の正式なものであることを示す重要な手続きです。
- 作成した報酬額表を、事務所のお客様から見やすい場所に掲示する。 来客が容易に目にして確認できる壁面などが一般的です。
これで報酬額表の作成と掲示は完了です。
作成した報酬額表は、一度作ったら終わりではなく、業務内容や経験の変化に応じて見直し、必要に応じて改訂することも考慮に入れましょう。
さて、報酬額表の作成や料金設定において、特に新人の方が悩むのが、統計データにないようなニッチな業務や、経験のない難しい業務の料金をどう決めるかです。
事前の見積もり段階では簡単そうに見えても、実際に業務に着手したら想定外の時間がかかったり、複雑な手続きが必要だったりして、「もっと報酬をもらっておけばよかった…」と後悔することもあるかもしれません。
このような未知の業務に直面した際に非常に頼りになるのが、経験豊富な先輩行政書士の存在です。
所属する支部の会合や研修会に積極的に参加し、質問しやすい、相談しやすい先輩を見つけておくことは、開業当初の大きな助けとなります。
料金設定だけでなく、業務の進め方、役所との折衝方法など、様々な実践的なアドバイスを得られるはずです。
先輩行政書士とのネットワークは、報酬額の判断が難しいケースだけでなく、行政書士業務を円滑に進める上で非常に重要な財産となるでしょう。
まとめ
開業行政書士にとって、報酬額表の作成と適切な料金設定は避けて通れない重要なステップです。
これは法律で定められた義務であると同時に、お客様への信頼構築や事務所経営の安定に直結するからです。
初めての経験で悩むことも多いと思いますが、行政書士会が提供するデータや近隣の事務所の料金設定を参考にし、地域性も考慮しながら、ご自身のサービスに見合った適正価格を見つけていきましょう。
そして、難しい判断に迷ったときは、積極的に先輩行政書士に助けを求めることをお勧めします。
この記事が、あなたの行政書士としての第一歩を応援する一助となれば幸いです。
この記事で解説した主なポイントは以下の通りです。
- 開業行政書士に「報酬額表」の掲示が義務付けられている理由
- 新人行政書士が直面する報酬額設定の壁と乗り越え方
- 報酬設定の参考にすべきデータと地域性の重要性
- 報酬額表の具体的な作成手順と作成後の注意点