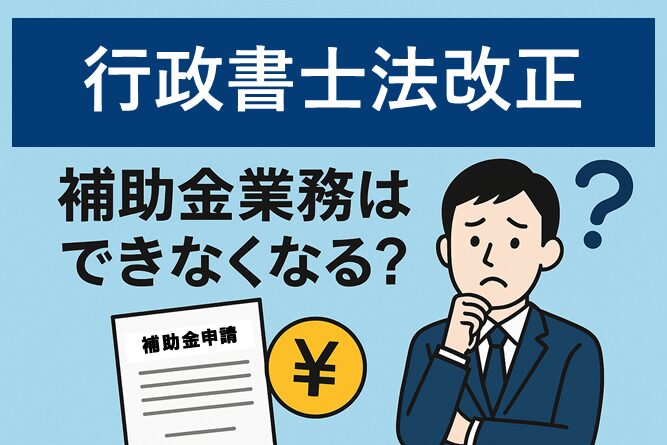
令和7年1月1日に行政書士法が改正されます。
ここで話題になっているのが、行政書士でないと補助金業務ができなくなるのではないか?
と補助金コンサルタントさんが危惧しているようです。
結論から言うと、補助金業務におけるコンサルタント、事業計画作成における助言や指導はいままでもこれからも行うことができます。
官公署に提出する書類の作成については、行政書士でないとできないということに変わりはありません。
補助金業務ができなくなるのか
何ができないかということについては、行政書士法を確認してみましょう。
改正前の行政書士法から一部抜粋
第1条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
行政書士法により、官公署に提出する書類(データを含む)を作成することが行政書士の独占業務であり、行政書士又は行政書士法人でない者は、この業務を行うことができない旨の記載があります。
補助金業務において、書類やデータが官公署に提出するものであれば、それ自体作成できないと規定されています。
改正により、報酬について「いかなる名目によらず」という文言が追記される
これによって、何かがかわるのかというと実は、特に変わる事はありません。
言い換えると、今まで補助金コンサル業務として官公署に提出する書類やデータを作成していたのであれば、そもそもが行政書士法違反であった。ということです。
例えば、コンサル業務のついでに無償で書類作成する。だとか、売買代金のついでに無償で書類作成する。なんてことができなくなる。
と言われていますが、そもそも、改正前から(名目を変えようが)報酬を得ての官公署へ提出する書類作成することは行政書士法違反となる可能性があります。
改正後からできなくなる。は間違えで、改正前からどんな名目であれ有償作成はできないことについて、改正によってより明確に示された。が正解となります。
行政書士には補助金業務における事業計画の作成は難しい、無理だという意見について
能力的に行政書士全員ができるかというと、その通り無理なことは間違いありません。
いかなる士業であれ、個人の能力・専門とする分野に違いはあります。
他の士業であれば(能力的に)全員ができる。と言っているのと同じことです。
本来の論点は能力的に作成できるかというところではなく、法律的に「官公署へ提出する書類を作成できるかどうか」という部分です。
行政書士法第19条の但し書きにあるとおり、「他の法律に別段の定めがある場合」は官公署に提出する書類の作成が可能ですので、その業務について法律で作成できる旨の規定があれば、行政書士でなくても行うことが可能です。
行政書士に限らず、○○士とつく国家資格は、法律によって規定されています。
士業者であれば、官公署に提出する書類であれば行政書士資格が必要ということは基本的なことなので、理解しているはずです。(いわゆる業際問題)
理解していた専門家であれば、作成までは行わずに事業計画の作成指導、助言、いわゆるコンサルタント業務を行っていたので何も問題はありません。
いわゆる士業者以外のコンサルタントなどは知らずに作成まで行っていた可能性があるかもしれません。
知らずに官公署へ提出する書類作成業務を行っていたのであれば、行政書士法違反に問われる可能性があることに違いはありません。
いわゆる業際問題
法律によって規定されている国家資格者のみが行うことができる独占業務(8士業)
| 国家資格 | 主な独占業務 | 主な書類提出先 |
| 弁護士 | 法律行為全般、訴訟事務 | 裁判所、法務局など |
| 司法書士 | 不動産の保存登記、商業登記の申請 | 法務局、裁判所 |
| 税理士 | 税務申告(無償であっても税理士以外は不可) | 税務署 |
| 弁理士 | 特許、実用新案、意匠、商標の申請 | 特許庁 |
| 土地家屋調査士 | 不動産の表題登記申請 | 法務局 |
| 社会保険労務士 | 社会保険に関する書類作成 | 厚生労働省、労働基準監督署、年金事務所、ハローワーク |
| 海事代理士 | 海事、船舶に関する申請、登記 | 海上保安庁 |
| 行政書士 | 官公署へ提出する書類の作成 | 官公署 |
弁護士に法律行為全般が認められており、司法書士や行政書士などはその一部について、法律の規定で認められているというイメージです。
したがって、行政書士法違反じゃないから大丈夫などと安心しても、弁護士法違反となるケースもあります。
コンサルティングの仕事は官公署へ提出する書類作成ではい
そもそもの話です。
コンサルティングの仕事は専門的な知見による、助言・提案や分析などを行うことです。
依頼に従ってレポートを作成し、顧客に提出することはあっても、官公署へ提出する書類を作成することではないはずです。
申請書類の作成はコンサルティング業務ではない。ということです。
両罰規定が追加される
いままで規定されていなかった両罰規定。
いわゆる士業法のなかで、行政書士法のみに規定がなかったものがようやく規定されました。
例えば社員が行った行政書士法違反業務について、改正後はその社員だけでなく、法人又はその代表者が同時に罰則の対象となります。
これからどうするべきか
個人でコンサル業務を行い、書類作成まで行う場合は、行政書士登録を行うことが必要です。
公認会計士や税理士等であれば、その資格をもって行政書士登録が可能ですが、その他の個人は先に行政書士試験に合格する必要があります。
法人でコンサル業務を行い、書類作成まで行う場合、社員に行政書士の登録をさせても、社員として行政書士業務をすることができません。
※名義貸しとなるため行政書士会の会則で規定されています。
会社の部署に行政書士部署を作成するようなことも認められていません。
したがって、行政書士との業務提携や顧問契約等などを行っていくことになるかも知れません。
まとめ
いままでも、改正後も、コンサル料、仲介料、請負代金などの名目で行った(その業務をするのに必要だから付帯して行った)官公署への提出書類作成は、行政書士資格が必要であることに変わりはありません。
能力的にできるできないかは問題ではなく、法律的にできるかできないかが論点である。
作成する書類やデータがどこに提出されるものなのかの確認が重要。
家族や知人が無償で行うことまで禁止しているわけではない。